モナド変換子
mtlとtransformers
前章でのモナドの説明は、罪のない嘘が少々交じっています。現代の Haskell のモナドライブラリは、概して、モナド変換子を使って書いた、より一般性のある形を使うのです。モナド変換子を使えば、モナドを合成して合成モナドを作ることができます。先ほど触れたモナドは、変換子の形のものを Identity モナドと合成した、特定の場合に特化したものとして扱うことができます。
| モナド | 変換子 | 型 | 変換子の型 |
|---|---|---|---|
| Maybe | MaybeT | Maybe a |
m (Maybe a) |
| Reader | ReaderT | r -> a |
r -> m a |
| Writer | WriterT | (a,w) |
m (a,w) |
| State | StateT | s -> (a,s) |
s -> m (a,s) |
type State s = StateT s Identity
type Writer w = WriterT w Identity
type Reader r = ReaderT r Identity
instance Monad m => MonadState s (StateT s m)
instance Monad m => MonadReader r (ReaderT r m)
instance (Monoid w, Monad m) => MonadWriter w (WriterT w m)
一般性の観点からは、mtl ライブラリはこれらのモナドに対する共通のインターフェースとして最も一般性がありますが、このライブラリ自体、上述の”基本的”なモナドを変換子へと一般化している transformers ライブラリに依存しています。
変換子
中核では、モナド変換子はモナディックな計算をスタック上で入れ子に出来るようにしています。ここで、様々なレベルの間で値をやりとりするための lift[持ち上げ]というインターフェースが提供されています。
lift :: (Monad m, MonadTrans t) => m a -> t m a
liftIO :: MonadIO m => IO a -> m a
class MonadTrans t where
lift :: Monad m => m a -> t m a
class (Monad m) => MonadIO m where
liftIO :: IO a -> m a
instance MonadIO IO where
liftIO = id
基盤にあるモナドクラスが法則を持つように、モナド変換子もいくつかの法則を持っています。
法則 1
lift . return = return
法則 2
lift (m >>= f) = lift m >>= (lift . f)
次のようにも書けます。
法則 1
lift (return x)
= return x
法則 2
do x <- lift m
lift (f x)
= lift $ do x <- m
f x
変換子の合成は外側から内側へと為されますが、ほどいていく際には内側から外側へと行く、と覚えておくと便利でしょう。
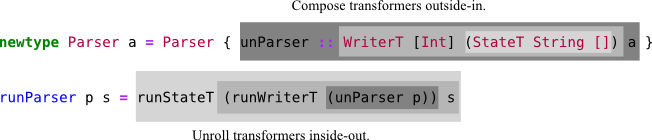
参照:
ReaderT
例えば、読み取りモナドには 3 つの形が可能性として存在します。1 番目は Haskell 98 のもので、今はもう使われませんが、教育上は有用です。transformers の変種と mtl の変種を合わせて紹介しています。
Reader
newtype Reader r a = Reader { runReader :: r -> a }
instance MonadReader r (Reader r) where
ask = Reader id
local f m = Reader $ runReader m . f
ReaderT
newtype ReaderT r m a = ReaderT { runReaderT :: r -> m a }
instance (Monad m) => Monad (ReaderT r m) where
return a = ReaderT $ \_ -> return a
m >>= k = ReaderT $ \r -> do
a <- runReaderT m r
runReaderT (k a) r
instance MonadTrans (ReaderT r) where
lift m = ReaderT $ \_ -> m
MonadReader
class (Monad m) => MonadReader r m | m -> r where
ask :: m r
local :: (r -> r) -> m a -> m a
instance (Monad m) => MonadReader r (ReaderT r m) where
ask = ReaderT return
local f m = ReaderT $ \r -> runReaderT m (f r)
ですから、ask の 3 つの変種は以下のようになると仮定できます。
ask :: Reader r a
ask :: Monad m => ReaderT r m r
ask :: MonadReader r m => m r
実用上は、最後のものだけが現代の Haskell では使われています。
基本
最も基本的な使い方では、外側の層に、T の付いた変種であるモナド変換子を使って、各層の間で明示的に lift し値を return せねばなりません。モナドは (* -> *) の種を持つので、モナドを受け取ってモナドにするモナド変換子は ((* -> *) -> * -> *) の種を持ちます。
Monad (m :: * -> *)
MonadTrans (t :: (* -> *) -> * -> *)
例えば、Reader と Maybe の両方のモナドを用いる合成計算を作りたければ、ReaderT の内側に Maybe を入れて ReaderT t Maybe a を作ればいいのです。
import Control.Monad.Reader
type Env = [(String, Int)]
type Eval a = ReaderT Env Maybe a
data Expr
= Val Int
| Add Expr Expr
| Var String
deriving (Show)
eval :: Expr -> Eval Int
eval ex = case ex of
Val n -> return n
Add x y -> do
a <- eval x
b <- eval y
return (a+b)
Var x -> do
env <- ask
val <- lift (lookup x env)
return val
env :: Env
env = [("x", 2), ("y", 5)]
ex1 :: Eval Int
ex1 = eval (Add (Val 2) (Add (Val 1) (Var "x")))
example1, example2 :: Maybe Int
example1 = runReaderT ex1 env
example2 = runReaderT ex1 []
この方法の根本的な限界は、lift.lift.lift や return.return.return をたくさんせねばならないということです。
newtype導出
newtype を使えば、単一コンストラクタのデータ型を、新たな別の型として、(単一コンストラクタの代数的データ型と違い)ボックスの出し入れによる実行時のオーバーヘッド無しに使うことができます。文字列や数値に対する newtype のラッパーを使えば、しばしば事故的なエラーを劇的に減らすことができます。-XGeneralizedNewtypeDeriving を使えば、基盤にある型のインスタンスの機能を復元することもできます。
{-# LANGUAGE GeneralizedNewtypeDeriving #-}
newtype Velocity = Velocity { unVelocity :: Double }
deriving (Eq, Ord)
v :: Velocity
v = Velocity 2.718
x :: Double
x = 6.636
-- 実行時には同じ種類の値ですが、コンパイル時には型エラーが捕捉されます!
err = v + x
newtype Quantity v a = Quantity a
deriving (Eq, Ord, Num, Show)
data Haskeller
type Haskellers = Quantity Haskeller Int
a = Quantity 2 :: Haskellers
b = Quantity 6 :: Haskellers
totalHaskellers :: Haskellers
totalHaskellers = a + b
Couldn't match type `Double' with `Velocity'
Expected type: Velocity
Actual type: Double
In the second argument of `(+)', namely `x'
In the expression: v + x
newtype導出をmtlライブラリの型クラスと一緒に使えば、変換のスタックで明示的に持ち上げる必要のない、平坦な変換子の型を作れます。例えば、下にあるのは読み取り、書き留め、状態のモナドからなる小さなスタックの機械です。
{-# LANGUAGE GeneralizedNewtypeDeriving #-}
import Control.Monad.Reader
import Control.Monad.Writer
import Control.Monad.State
type Stack = [Int]
type Output = [Int]
type Program = [Instr]
type VM a = ReaderT Program (WriterT Output (State Stack)) a
newtype Comp a = Comp { unComp :: VM a }
deriving (Monad, MonadReader Program, MonadWriter Output, MonadState Stack)
data Instr = Push Int | Pop | Puts
evalInstr :: Instr -> Comp ()
evalInstr instr = case instr of
Pop -> modify tail
Push n -> modify (n:)
Puts -> do
tos <- gets head
tell [tos]
eval :: Comp ()
eval = do
instr <- ask
case instr of
[] -> return ()
(i:is) -> evalInstr i >> local (const is) eval
execVM :: Program -> Output
execVM = flip evalState [] . execWriterT . runReaderT (unComp eval)
program :: Program
program = [
Push 42,
Push 27,
Puts,
Pop,
Puts,
Pop
]
main :: IO ()
main = mapM_ print $ execVM program
newtype コンストラクタでのパターンマッチングはコンパイルされると無くなります。例えば、extractB 関数は、extractA と違い、MkB コンストラクタを調べません。MkB は実行時には存在せず、コンパイル時にあるものにすぎないからです。
data A = MkA Int
newtype B = MkB Int
extractA :: A -> Int
extractA (MkA x) = x
extractB :: B -> Int
extractB (MkB x) = x
効率
2 番目のモナド変換子の法則は、持ち上げ操作を連続して行ったものを配列 (sequence) することは、外側のモナドへと結果を持ち上げることと、意味論的に等価である、ということを保証しています。
do x <- lift m == lift $ do x <- m
lift (f x) f x
同じ結果を出すことは保証されていますが、モナドのレベルの間で結果を持ち上げる操作はコスト無しに出来ることでは無く、モナド上で走査やループする関数を行うと、しばしばコストがかさむのです。例えば、下記の 3 つの左辺の関数は全て右辺の関数より非効率です。右辺の関数は基盤のモナドで束縛をしていますが、左辺の関数は毎回毎回持ち上げをしているのです。
-- Less Efficient More Efficient
forever (lift m) == lift (forever m)
mapM_ (lift . f) xs == lift (mapM_ f xs)
forM_ xs (lift . f) == lift (forM_ xs f)
モナド射
lift :: Monad m => m a -> t m a
hoist :: Monad m => (forall a. m a -> n a) -> t m b -> t n b
embed :: Monad n => (forall a. m a -> t n a) -> t m b -> t n b
squash :: (Monad m, MMonad t) => t (t m) a -> t m a
未完成
参照: